- INFLUFECT TOP
- コラム
- RED(小紅書)とは?中国での圧倒的な影響力と日本企業の活用可能性を解説【2025年最新版】
RED(小紅書)とは?中国での圧倒的な影響力と日本企業の活用可能性を解説【2025年最新版】
最終更新日 2025年8月1日(Fri)
記事作成日 2025年8月1日(Fri)

中国国内で独自の発展を遂げ、圧倒的な影響力を持つSNS「RED(小紅書)」が、日本企業のマーケティング施策として注目を集めています。リアルな体験レビューを積極的に行い、主に若年層の女性の購買にも大きな影響を与えているといわれています。
この記事では、REDが中国市場で流行する背景や主な特徴を整理し、リデルが考える日本企業としての活用方法や可能性を詳しく解説します。
「REDとはどんなSNS?」「日本企業が活用するメリットは?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
RED(小紅書)とは?

RED(小紅書)は中国で圧倒的な影響力を持つSNSプラットフォームです。まずはその基本概要と特徴について詳しく見ていきましょう。
REDの基本概要とユーザー規模
RED(小紅書)は、中国国内で若年層を中心に爆発的な人気を誇るコンテンツ共有型のSNSプラットフォームです。InstagramとPinterestを融合したような、写真や動画を活用したユーザー同士の口コミやレビューが特徴です。
RED(小紅書)のユーザー数は、3.3億人(2024年11月)に達し、アメリカでのアクティブユーザー数も増えています。
RED(小紅書)は、世界中でも1つのプロダクトにて運営され本土版・グローバル版のような分類わけはありません。実際に利用している約10%は海外のユーザーであることも特徴で、台湾でのダウンロード数も500万を超えています。
「RED(小紅書)を見れば、世界中にある良いものを見つけられる」というコンセプトのもと運営されています。
REDの主な特徴と機能
日本ではまだ一部のユーザーに限られたSNSですが、中国国内では「知らない人はいない」と言えるほど、生活に深く浸透した情報収集ツールとなっています。特に買い物や旅行に関する意思決定においては、REDを使わない人のほうが少数派といっても過言ではありません。
ジャンルの幅も広く、「食品」「家電」「コスメ・ファッション」「映画とテレビ」「読書」「フィットネス」など多岐にわたります。もはや検索エンジンのように、「知りたいことがあればまずはREDで調べる」という行動が一般化しています。
この圧倒的な存在感を支えるのが、AIによる高度なパーソナライズ機能です。ユーザーの興味関心に応じて関連性の高い投稿を表示し、良質なコンテンツはより多くの人の目に触れる仕組みとなっています。
さらに、ブックマーク機能により「買い物リスト」の整理がしやすく、タグによる検索性の向上、EC機能との連動で個人店舗の出店も可能と、生活のあらゆるシーンに寄り添う万能プラットフォームへと進化を遂げています。
REDの市場における位置づけ
ここ数年で注目度が高まってきたSNSともいえ、若い女性を中心に必ず使用するSNSとしても認知されています。現在、RED(小紅書)は中国市場でのマーケティングに欠かせないプラットフォームとなっています。
利用者の趣味嗜好に基づきコンテンツを表示させることもあり、コンテンツの質によるPV上昇も行っています。RED(小紅書)にはブックマーク機能もあるため「買い物リスト」の整理もしやすく、使い安い工夫をしています。
また、商品情報にタグをつけたことで情報を見つけやすいように変更し、EC機能による個人経営店舗での販売にも力を入れています。
RED(小紅書)流行の背景と中国市場の特徴

RED(小紅書)が中国で急速に普及した背景には、独特なSNS環境と文化的要因があります。どうしてここまで広まったのか、その理由を紐解いてみます。
中国国内SNS環境とREDの台頭
中国ではFacebookやInstagramといった海外SNSの利用が制限されており、独自のSNSエコシステムが発達しています。その中でも特に注目を集めているのがRED(小紅書)で、近年急速にユーザー数を拡大させています。
RED(小紅書)の成長を支えているのが「種草(シードプランティング)」と呼ばれる共感型レビュー文化です。ユーザーが実際に体験した商品やサービスの口コミが購買行動に直結するため、プラットフォーム側も「不正投稿の排除」や「観光地写真詐欺対策」など、信頼性を確保する運営体制を徹底しています。
信頼性の確立とユーザーファーストの取り組み
RED(小紅書)がここまで信頼を集めてきたのは、「ユーザーにとって本当に役立つ情報を届けたい」という姿勢を徹底しているからです。
たとえば、旅行先の写真が実際とは全然違うと指摘された際には、運営側が正式に謝罪し、「実際に行ってがっかりした観光地ランキング」を公開。ユーザーの声を真摯に受け止め、よりリアルな情報発信を促す取り組みを行いました。こうした姿勢が、多くの人に信頼されるSNSへと成長した理由のひとつと言えるでしょう。
RED(小紅書)の現状とマーケティングにおける役割

RED(小紅書)は、ただのSNSではありません。「良かった点」だけでなく「正直、ここ
はイマイチだった」というリアルな感想が購買に直結する、他にはないレビュー主導型のプラットフォームです。この記事では、そんなREDを企業がどう活用しているのか、日本企業はどう対応しているのかを解説します。
企業活用の現状とビジネス機能
RED(小紅書)は多くの外資系企業が公式アカウントを開設し、活発なキャンペーンも展開しています。RED(小紅書)の対策を行い、話題化を実現し需要を喚起したうえで、ECサイトの爆売れという成功パターンを確立させています。
RED(小紅書)のビジネスアカウント認証を取ると、アプリの中でECサイトを作成できるようになります。中国で話題になっているライブコマース機能の利用もできるようになるため、ビジネスを広げたい企業にとっても欠かせません。ただし、ECサイトで購入できるのは中国人民元にのみ限られています。
信頼性の確立とユーザーファーストの取り組み
日本でもRED(小紅書)に対しての意識は広がりつつありますが「Instagramの中国版?」といった表面的な理解にとどまるケースがほとんどです。RED(小紅書)についてよくわかっていないという対応の遅れが大きなリスクとして知られています。
インバウンド対策としてのRED活用の重要性
いま、中国からの観光客は回復基調にあり、特に都市部だけでなく地方への関心も高まっています。たとえば「一度は行ってみたい温泉地」として検索された道後温泉などは、実際にRED上でも多数のリアルな体験投稿がなされ、観光地選びの参考にされています。
REDでは「実際どうだったか」「期待外れだった部分」までもが赤裸々に語られ、単なる宣伝とは一線を画した「生活者目線」の情報が重視される傾向があります。日本国内ではInstagramやYouTubeの活用に注力している企業が多い一方で、中国圏向けのプロモーションにおいてRED対策を怠ると、情報の起点から外れてしまうリスクもあります。
日本企業によるRED(小紅書)活用事例

現在、株式会社unbotの支援により、愛媛県は在日中国人インフルエンサーを起用したRED(小紅書)でのプロモーション施策を展開しています。
本章では、その施策プロセスや結果、導入時の注意点を解説します。
愛媛県のRED成功事例
株式会社unbotは中華圏向けのデジタルマーケティングに特化した企業で、2023年より愛媛県の国際観光テーマ地区推進協議体と連携し、REDを活用した情報発信に取り組んでいます。
インフルエンサーを実際に現地へ招致し、道後温泉、松山城、しまなみ海道などの観光体験を発信。グルメや観光といった複数のテーマで投稿を行い、その反響をデータ分析することで、愛媛県の訴求ポイントを可視化する施策となっています。
この取り組みによって、RED内での愛媛県に関する投稿数が増加し、指名検索数も大きく伸長しました。2025年に入り、愛媛県における訪日外国人の国別ランキングで中国が1位となったことからも、プロモーション強化の重要性が浮かび上がります。
この施策は、愛媛県の認知拡大とインバウンド需要のさらなる後押しにつながるものとして注目されています。
日本企業がRED(小紅書)を導入する注意点
日本企業がRED(小紅書)を導入する際には、「中国広告法」を意識した対策を行うことをおすすめします。一般消費者からの口コミもビジネスに活かされる部分になりますし、RED(小紅書)のアルゴリズムを十分に理解したうえで運営をしていく必要があります。
また、REDでの発信は、日本のSNSのような「盛った投稿」が逆効果になるケースがあります。例えば、「最高だった!」の連発や過度な演出は、コメント欄で「サクラ認定」されてしまうことも。現地ユーザーの目線を理解せずに投稿すると、ブランド毀損にもつながりかねません。
「少し不便だったけど、こんな工夫があった」「◯◯は期待より控えめだったけど、△△がすごく良かった」などの等身大の語り口が共感される傾向にあります。これは日本の「お客様目線マーケティング」とも通じる部分があり、情報の出し方ひとつで信頼感が大きく左右されるのがRED特有の難しさであり面白さです。
日本企業にとっては、「いいところだけを伝える」これまでの広告感覚をいったん手放す必要があります。
REDがもたらす新たなマーケティングチャンス

企業やブランドがREDを活用することで、「買いたい」と思っている層へ自然な形でアプローチできるチャンスが広がっています。
- 購買意欲の高いユーザー層へのアプローチ方法
- 信頼を積み上げる公式アカウント運営
- 成果を高めるインフルエンサー施策やタグ活用
上記のようなREDならではの戦略について解説します。
高い購買意欲を持つユーザー層へのアプローチ
RED(小紅書)は、すでに「買うか検討している」ユーザーが多く集まる場です。検索やタグ経由で商品にたどり着き、レビューを読み込んだうえで判断する傾向があります。
そのため、「おすすめ!」という一方的なアピールではなく、正直な感想やややネガティブな意見も含めた「リアルな声」のほうが信頼されやすいのが特徴です。共感を得るには、インフルエンサー選びでも「専門性」よりも「生活者目線」が重視されます。
また、ブックマーク機能を活用して「買うかもしれない」商品を保存する文化が根付いており、投稿は「購入前の意思決定を左右する資産」として長く活きることも忘れてはいけません。
公式アカウント運営とファンコミュニティ形成
REDの公式アカウントは、「すぐに売る」よりも「信頼を少しずつ積み上げる」ための場として運用するほうが成果につながりやすいでしょう。
例えば、新商品の紹介だけでなく「開発背景」や「改善の試行錯誤」など、ブランドの姿勢や価値観を伝える投稿がユーザーの共感を得て、結果的にフォロワーとの長期的な関係構築につながります。
投稿がすぐに売上に直結しなくても、「また見たい」「感じがいい」と記憶に残るアカウント運営が、将来の購買につながる土台になります。
インフルエンサー施策とその他の展開
REDでのインフルエンサー施策は、「誰が紹介するか」だけでなく「どう使うかを見せること」が成果を左右します。
美容ジャンルでいえば、「朝使うと崩れにくい」「外出先でも塗り直しやすい」といった具体的な使い方の紹介が、ユーザーの購買意欲を後押ししています。
また、ライブコマースや広告、タグ戦略などを組み合わせることで、投稿を軸にした面での広がりをつくることも可能です。単発ではなく、全体設計で成果を狙うことが重要です。
まとめ
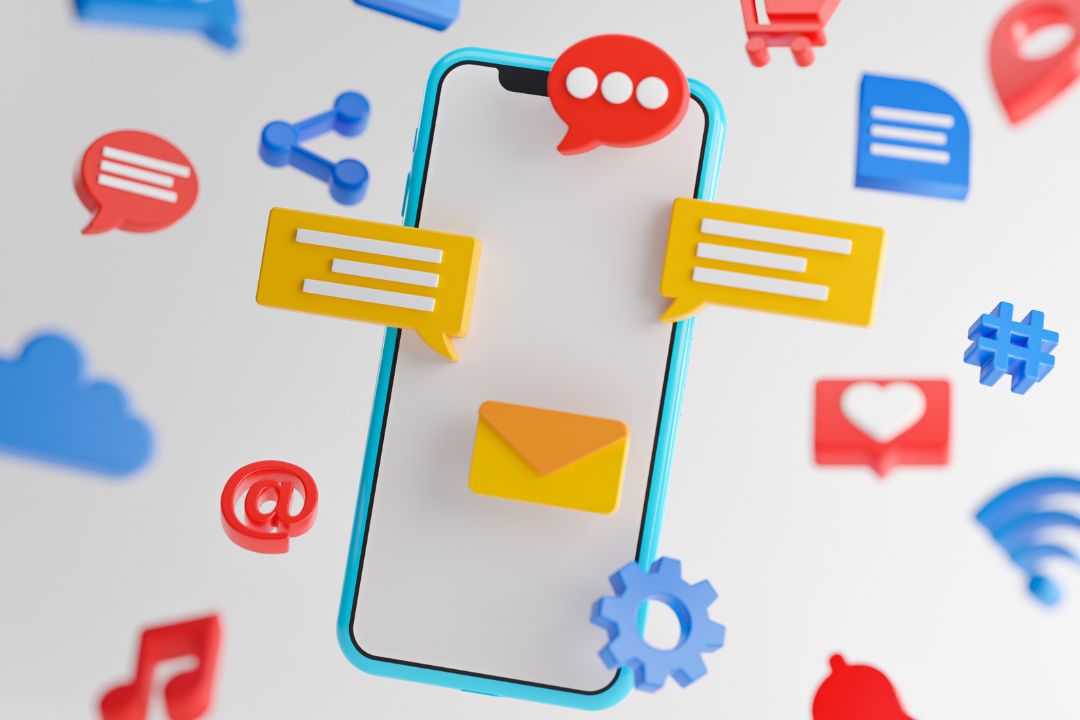
RED(小紅書)は中国の巨大な消費市場に効果的にアプローチするためにも欠かせない、強力なプラットフォームの一つです。中国マーケティング戦略をより加速させたい企業にとっても、早急な対策が必要と言えるでしょう。
SNSマーケティングに特化している私たちリデルは、REDを活用したマーケティング施策やキャンペーンを企画・運用し、日本企業の中国市場での成功を全面的にサポートします。
中国市場への進出やインバウンド需要の獲得にご興味がある方は、ぜひリデルまでご相談ください。





