- INFLUFECT TOP
- コラム
- インフルエンサーマーケティング会社の選び方 完全ガイド|費用相場・メリット・注意点も徹底解説
インフルエンサーマーケティング会社の選び方 完全ガイド|費用相場・メリット・注意点も徹底解説
最終更新日 2025年10月27日(Mon)
記事作成日 2025年10月24日(Fri)
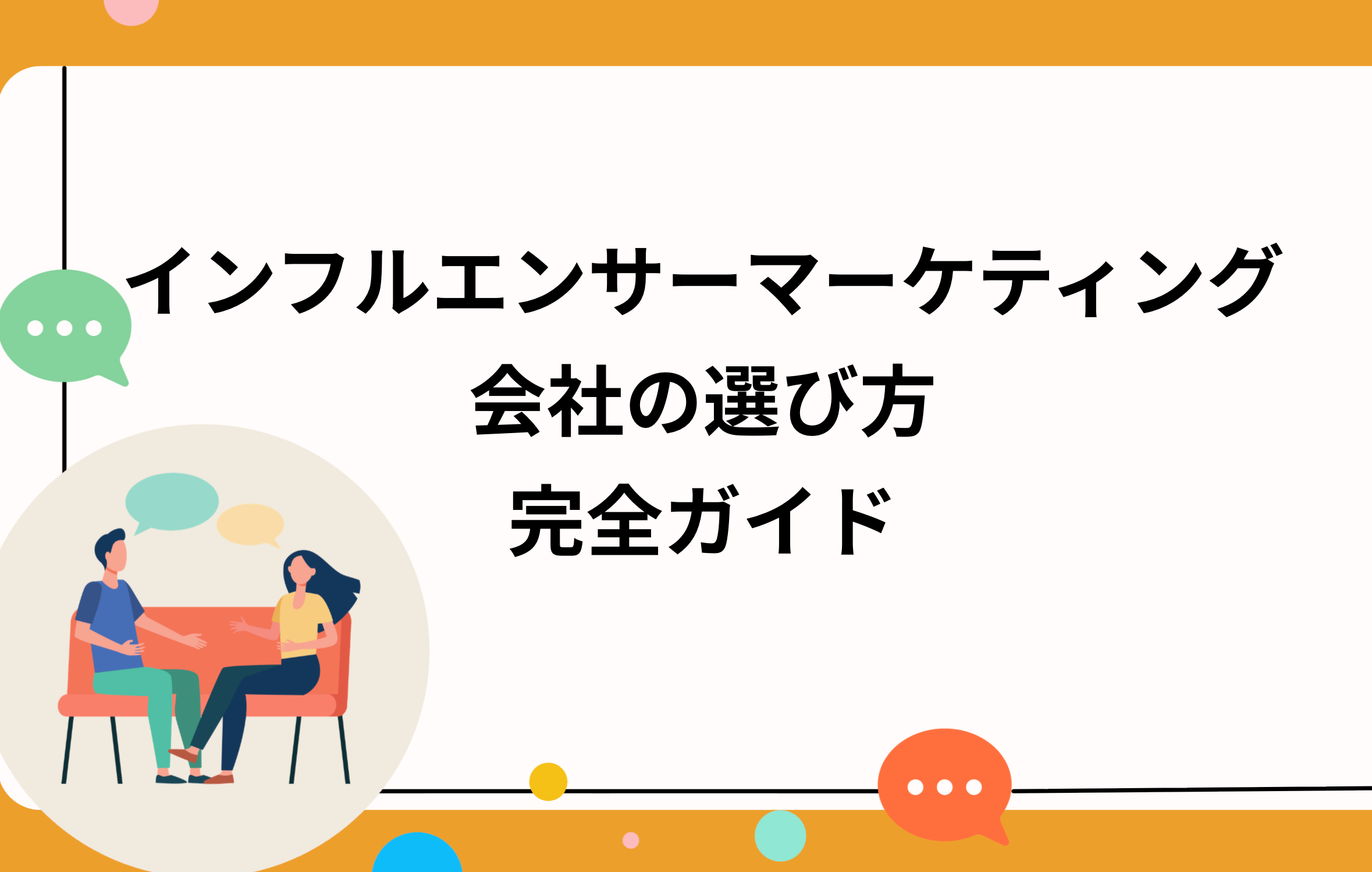
SNSを活用したインフルエンサーマーケティングは、今や企業の主要なPR戦略として欠かせない存在となりました。
商品の魅力やブランドの想いを、信頼できるインフルエンサーを通して発信することで、消費者の共感を呼び起こす効果が期待できます。
一方で、「どのくらいの費用が必要なのか」「どの会社に依頼すべきか」といった具体的な判断に迷う担当者も少なくありません。
本記事では、INFLUFECTのデータをもとに、インフルエンサーマーケティング会社の費用相場や報酬体系(固定報酬制・成果報酬制)、活用のメリットと注意点、そして失敗しない選び方の5つのポイントをわかりやすく解説します。
初めて施策を検討する企業はもちろん、既に導入済みの企業にも役立つ、成果を最大化するための実践ガイドです。
目次
執筆者:萩原雄太
SNS・コミュニティマーケティング専門企業「LIDDELL」取締役。
みずほ証券でトップセールスを経験後、2017年よりLIDDELLに参加。先進企業を含む多様なクライアントに対して、SNS戦略検討やファンマーケティングを推進。AI・システム開発・コミュニティ設計にも関わり、100名規模のクラウドワーカーチームを
統括している。
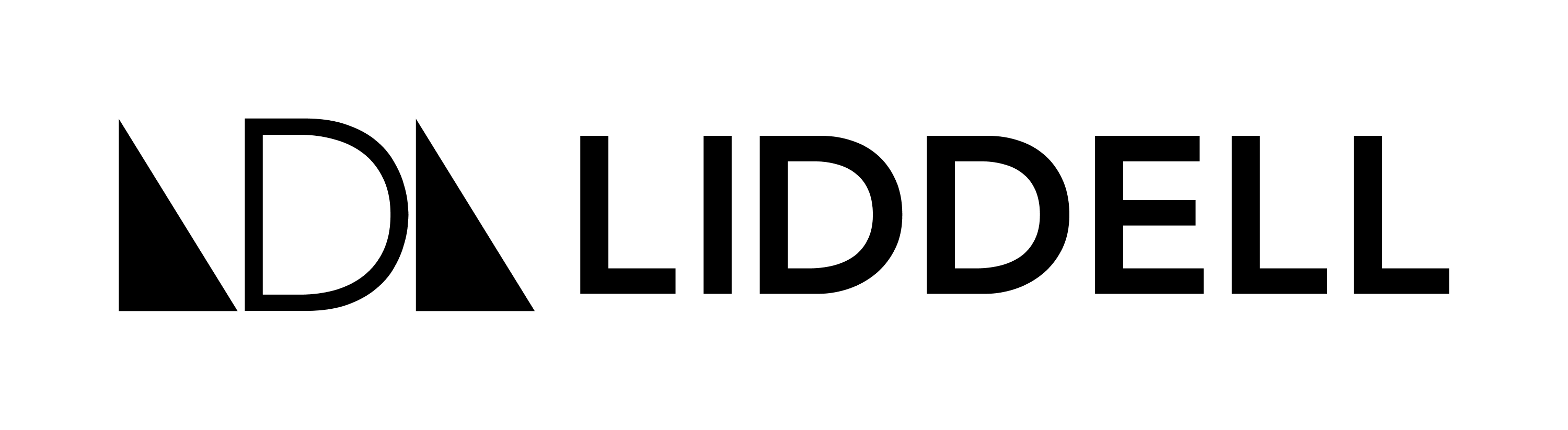
運営会社:リデル株式会社
SNS・インフルエンサーマーケティングに特化した企業。
7,000社との取引実績を持ち、5万名を超えるインフルエンサーと連携。マーケティング戦略からキャスティング、投稿
運用、AI分析、Web3領域まで一気貫で対応。
個人の影響力を超えて「共創型マーケティング」の実現を得意とする。
インフルエンサーマーケティング会社の失敗しない選び方 5つのポイント
インフルエンサーマーケティングの成果は、どの会社と組むかによって大きく変わります。
同じ広告費を投じても、戦略設計・キャスティング・分析力の差が結果に直結するため、
「安さ」や「知名度」だけで選ぶのは危険です。
理想的なパートナーとは、単なる仲介業者ではなく、
企業のブランド戦略を理解し、目標に沿った施策を共に設計してくれる存在です。
ここでは、失敗を防ぐために押さえておきたい5つの選定ポイントを詳しく解説します。
【ポイント①】インフルエンサーの数と質は十分か
まず確認すべきは、提携・登録しているインフルエンサーの規模と質です。
数が多いほど選択肢が広がりますが、重要なのは「数」よりも「質」。
「企業のターゲット層にマッチするフォロワーを持っているか」
「投稿のエンゲージメント率(いいね・コメント・保存など)が高いか」
を確認しましょう。
たとえば、フォロワー10万人でもエンゲージメント率が1%未満なら実質的な影響力は限定的です。
一方、フォロワー5千人でもコメントやシェアが多い“マイクロインフルエンサー”は、
購買行動を喚起しやすい傾向にあります。
また、インフルエンサーとの関係性の深さもチェックすべき要素です。
単に「登録制」ではなく、会社が本人と直接契約し、
活動履歴や実績を把握しているかどうかで信頼性が大きく変わります。
確認ポイント:
- 提携インフルエンサー数、フォロワー層の属性
- 平均エンゲージメント率(3〜5%以上が理想)
- 本人確認・実績データの有無
- マイクロ〜メガ層まで幅広い層をカバーしているか
【ポイント②】対応できるジャンルやSNSの幅が広いか
会社によって得意分野は異なります。
美容・ファッション・旅行・飲食などの業界特化型の会社もあれば、
複数のSNS(Instagram・YouTube・TikTok・Xなど)を横断的にカバーする総合型の会社もあります。
自社の商材や目的に応じて、どのプラットフォームで訴求するのが最も効果的かを提案できる企業を選びましょう。
主なプラットフォームの特徴:
- Instagram/TikTok → 商品ビジュアルや短尺動画による“直感的訴求”に強い
- YouTube → ストーリーテリングや使用レビューなど“深い理解訴求”に向く
- X(旧Twitter) → リアルタイム性や話題拡散に強い
また、SNS間の連携(例:TikTokで拡散しInstagramで詳細訴求)を提案できる会社は、戦略性が高いといえます。
【ポイント③】信頼できる実績があるかどうか
実績は、その会社の「再現力」を測る最も確実な指標です。
過去にどんな業界・企業を支援し、どんな成果を上げたかを確認することで、
自社との親和性や期待できる効果を具体的にイメージできます。
特に注目すべきは、事例の具体性とデータの透明性です。
「売上〇%向上」「フォロワー〇万人増加」「CV数〇倍」
などの数値が明示されていれば信頼性が高いです。
一方、「多数の企業で採用実績あり」など抽象的な表現だけの会社は要注意です。
また、クライアント企業のロゴ掲載や共同セミナーなど、信頼関係の証拠があるかも評価ポイントです。
確認ポイント:
- 自社業界や目的に近い成功事例があるか
- 成果データが定量的に示されているか
- 導入実績企業や提携実績が公表されているか
- 効果測定やレポートの仕組みが整っているか
【ポイント④】問い合わせ時の対応が丁寧かどうか
意外と見落とされがちですが、
初回問い合わせの対応品質は会社選定における重要な判断材料です。
質問への回答スピード、説明のわかりやすさ、担当者の提案姿勢などから、
契約後の対応レベルを推測できます。
問い合わせ時に、担当者が企業の課題を丁寧にヒアリングし、的確な提案を行っているかどうかを観察しましょう。
逆に、「すぐに契約を促す」「具体的な質問に答えない」場合は注意が必要です。
また、返信のスピードやフォロー体制も重要な評価軸です。
迅速かつ誠実な対応をする会社は、案件進行中のトラブル対応や修正にも柔軟に対応できる傾向があります。
確認ポイント:
- 問い合わせへの返信スピード(24時間以内が理想)
- 説明や見積の透明性
- 契約前に具体的なシミュレーション提案があるか
- 対応の丁寧さ・親身さ
【ポイント⑤】自社特有の課題に即した提案をしてくれるか
最も重要なのが、「自社の状況を理解した上で提案してくれるか」です。
多くの会社がパッケージ化されたプランを提示しますが、
本当に成果を出すには、自社の課題・目標・リソースに合わせたカスタマイズ提案が不可欠です。
たとえば、「フォロワー増加」ではなく、
「地方エリアでの来店促進」や「特定世代へのブランド浸透」など、
目的に沿ったKPIを設定してくれるかを確認しましょう。
さらに、提案内容が「手段中心」ではなく、
課題解決型(Whyから設計する)であるかどうかも見極めのポイントです。
インフルエンサーの選定だけでなく、
投稿スケジュール、広告併用、効果測定までを一貫して提案できる会社は信頼性が高いです。
確認ポイント:
- 企業の現状・課題を的確に理解しているか
- 提案が目的ベース(売上・認知・エンゲージメント)で設計されているか
- 定量・定性の両面で効果を検証できる仕組みがあるか
- 長期的な改善提案を前提にしているか
インフルエンサーマーケティング会社の費用相場
SNSを通じたインフルエンサーマーケティングは、
企業規模を問わず効果的なプロモーション手段として定着しています。
しかし、実際に施策を検討する際に最も悩ましいのが、
「どのくらいの費用が妥当なのか」「どの水準でROI(投資対効果)が見込めるのか」
という点です。
インフルエンサーへの依頼費用は、一般的に「固定報酬制」または「成果報酬制」で構成されます。
加えて、企業の目的や支援範囲に応じて、
月額ベースのマーケティング支援プランを選択するケースも増えています。
この記事では、INFLUFECT公式情報と一般的な相場感とその効果指標(ROI・成功率)の表を基に、
企業規模ごとの費用相場と得られるリターンの目安を整理します。
| 価格帯 | サービス内容 | 対象企業 | 平均ROI | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 月額5万円〜15万円 | 基本投稿代のみ | 個人事業主・スタートアップ | 178% | 42% |
| 月額15万円〜30万円 | 戦略設計・コンテンツ制作 | 中小企業 | 285% | 67% |
| 月額30万円〜60万円 | 包括戦略・高度分析・最適化 | 中堅企業・成長企業 | 523% | 87% |
| 月額60万円〜100万円 | 統合マーケティング・専任チーム | 大企業・上場企業 | 487% | 91% |
固定報酬制
固定報酬制は、投稿内容や納期をあらかじめ決めて、一定の報酬を支払う方式です。
一般的な目安は、「フォロワー数×1〜5円」で、フォロワー1万人なら1〜5万円程度が相場です。
ただし、費用は、
-
-
- 使用するプラットフォーム(例:YouTubeは動画制作で高額、Instagramは比較的安価)
- 投稿形式(静止画より動画・ライブ配信が高単価)
- 分野の専門性(美容・医療などは単価が高い)
- 投稿の再利用の有無
-
によって変動します。
固定報酬制は、事前に費用を把握できるため、ブランド認知やイメージ向上を狙うキャンペーンに適しています。
成功報酬制
成果報酬制は、実際に成果が出た分だけ支払う方式で、
売上やアプリダウンロード、資料請求、予約数などの成果を基準に報酬を決めます。
報酬発生の条件は、
-
-
- アプリダウンロード1件につき◯◯円
- 無料相談の申し込み1件につき◯◯円
- ユーザーがECサイトで買い物した額の◯%
-
のように異なります。
報酬の目安とされるのは、売上に対して5〜30%程度の金額です。
企業はリスクを抑えて始められる一方、
成果を正確に把握するためにURLトラッキングや専用コードなどの計測体制の整備が必要です。
成功報酬制は、ROI(投資対効果)を明確に把握したい企業に向いています。
インフルエンサーマーケティング会社を活用する3つのメリット
インフルエンサーマーケティングを自社内で完結させることも不可能ではありません。
しかし、実際に成果を上げている多くの企業は、
専門のマーケティング会社やプラットフォームを戦略的に活用しています。
その理由は、個別のインフルエンサーを探して依頼するよりも、専門会社を通じて施策全体を設計・管理した方が、
費用対効果・業務効率・リスク管理のすべてにおいて優位性が高いためです。
以下では、企業が専門会社を利用することで得られる主な3つのメリットを詳しく紹介します。
【メリット①】適切なインフルエンサーを選定でき、成果につながる
インフルエンサー選定は、キャンペーン成功の最重要要素です。
マーケティング会社は、独自のデータベースや分析ツールを活用し、
フォロワー属性(年齢・性別・地域など)、エンゲージメント率、過去の投稿テーマ、拡散力などを数値的に評価します。
この分析により、単にフォロワー数が多い人を選ぶのではなく、
実際に購買・申し込み・来店といった成果につながりやすいインフルエンサーをマッチングできます。
また、INFLUFECTのようなプラットフォームでは、
案件内容や希望条件に合うインフルエンサーを迅速に提案できるため、
自社で一からリストアップする手間を大幅に削減できます。
結果として、無駄な広告費を減らし、ROIを最大化できる点が大きな利点です。
【メリット②】工数を削減し、コア業務に集中できる
インフルエンサーマーケティングは、一見シンプルに見えて実際には多くの手間が発生します。
「投稿スケジュール管理」「コメント対応」「分析レポート作成」などの日々の細かい運用タスクが積み重なることで、
担当者が本来注力すべき戦略業務や提案活動の時間を奪ってしまうことも少なくありません。
マーケティング会社を活用することで、これらの作業を包括的に代行してもらうことができ、
社内の工数削減と生産性向上の両立が実現します。
実際に、以下のような業務削減効果が見込まれます。
| 削除できる業務 | 週間工数 | 年間削減時間 | 生産性向上効果 |
|---|---|---|---|
| コンテンツ企画・制作 | 8時間 | 416時間 | 戦略業務に集中可能 |
| 投稿・管理作業 | 4時間 | 208時間 | 顧客対応時間増加 |
| コメント・DM対応 | 3時間 | 156時間 | 商談・提案活動拡大 |
| 分析・レポート作成 | 2時間 | 104時間 | 改善施策の立案強化 |
【メリット③】ステマや炎上のリスクを低減できる
SNSを活用したPRでは、法令やプラットフォームのガイドライン遵守が欠かせません。
「PR表記をしていなかった」「誤解を招く表現になっていた」といった投稿が炎上につながる事例も増えています。
マーケティング会社は、こうしたリスクを未然に防ぐため、
広告表記・ハッシュタグ表記(#PR、#提供など)のルールや、投稿前の内容確認・修正フローを徹底しています。
また、投稿後のモニタリングやトラブル対応も行うため、企業側は安心してキャンペーンを実施できます。
さらに、法令・景品表示法・薬機法などの専門知識を持つ担当者が在籍している会社も多く、
適正なPR運用とブランド保護の両立が可能です。
インフルエンサーマーケティング会社を活用する際の2つの注意点と対策
インフルエンサーマーケティング会社の活用には多くのメリットがありますが、
一方で「費用面」や「依頼先の選定」など、注意すべきポイントも存在します。
特に初めて外部パートナーを導入する企業は、コスト構造や業務分担の範囲を正確に把握しておかないと、
「思ったような成果が出ない」「予算に対して効果が見合わない」といった課題が生じる可能性があります。
こうしたリスクを事前に理解し、適切に対策を講じることで、
インフルエンサーマーケティングをより戦略的かつ持続的に活用することが可能になります。
以下では、特に注意すべき2つのポイントと、その対処法を解説します。
【デメリット①】初期投資のコスト負担が大きい
インフルエンサーマーケティング会社を利用する際、
最初に直面するのが「コスト」の問題です。
自社で直接インフルエンサーに依頼する場合と比較すると、
仲介手数料・ディレクション費・分析レポート費などが加算されるため、
初期費用が高く見えるケースがあります。
特に、月額契約型のプラン(例:30万〜60万円/月など)では、
「どの程度のリターンが見込めるのか」「社内で再現できないのか」といった懸念を抱く企業も多いでしょう。
しかし、重要なのは「コスト単体」ではなく「投資対効果(ROI)」で判断することです。
例えばINFLUFECTの調査では、月額30万〜60万円規模の包括的運用を行った企業の平均ROIは523%と高く、
戦略的な施策によって初期費用を上回る成果を得られる可能性が示されています。
また、専門会社はキャンペーン終了後のデータ分析を通じて「PDCAサイクル」を継続的に回すため、
単発の依頼よりも長期的な効果が期待できます。
対策:
まずは小規模テスト(数十万円単位)から始め、効果を数値で確認しながら投資規模を拡大するのが理想的です。
成功報酬型の契約形態を導入すれば、費用リスクを抑えながら運用を試すことも可能です。
【デメリット②】依頼先の選定を誤ると成果につながらない
マーケティング会社はそれぞれに強みを持っています。
美容・コスメに特化した会社、旅行・観光系のプロモーションが得意な会社、BtoB領域を中心に支援する会社など、
得意分野や提携インフルエンサー層が異なるため、自社の業界特性に合わない企業を選ぶと期待する効果が得られないリスクがあります。
また、対応範囲にも差があります。
「キャスティングのみ」「投稿内容の監修まで」「効果測定・レポート作成を含む」など、
サービス内容を事前に確認しておかないと、想定外の業務負担が社内に残る可能性もあります。
会社によっては「フォロワー数重視」「エンゲージメント率重視」「コンバージョン重視」など評価基準も異なり、
自社のKPI(売上・CV数・ブランド認知など)と一致していないと、効果測定の方向性がずれてしまいます。
対策:
-
-
- 事前に 実績・得意業界・支援範囲・分析体制 を確認し、
複数社から見積・提案を取り比較検討する。 - 自社の目標(例:売上向上 or 認知拡大)を明確に伝え、
どの指標で効果を測るかを契約段階で合意しておく。 - 可能であれば、担当者レベルでの相性(対応の速さ・提案内容の質)
もチェックする。
- 事前に 実績・得意業界・支援範囲・分析体制 を確認し、
-
これらを丁寧に行うことで、無駄な出費や方向性のズレを防ぎ、長期的な信頼関係を構築できます。
まとめ|インフルエンサーマーケティングは「コスト」ではなく「成長への投資」
インフルエンサーマーケティングは、単なる宣伝ではなく、
企業のブランドを育てるための投資です。
費用を「コスト」として削減するのではなく、
共感と信頼を生む戦略的な投資として活用することが重要です。
費用相場や契約形態を理解し、信頼できるパートナーを選ぶことで、
ROI(投資対効果)を高め、長期的なブランド成長につなげることができます。
インフルエンサーマーケティングの成功は、
目的の明確化・最適な会社選び・継続的な改善の3つにかかっています。
正しい知識と戦略をもって取り組めば、
その費用は“広告費”ではなく、企業の未来を支える成長投資となるでしょう。





