- INFLUFECT TOP
- コラム
- コンバージョン最大6倍!インフルエンサーの「信頼」を活かす体験コンテンツ広告戦略
コンバージョン最大6倍!インフルエンサーの「信頼」を活かす体験コンテンツ広告戦略
最終更新日 2025年10月15日(Wed)
記事作成日 2025年10月15日(Wed)
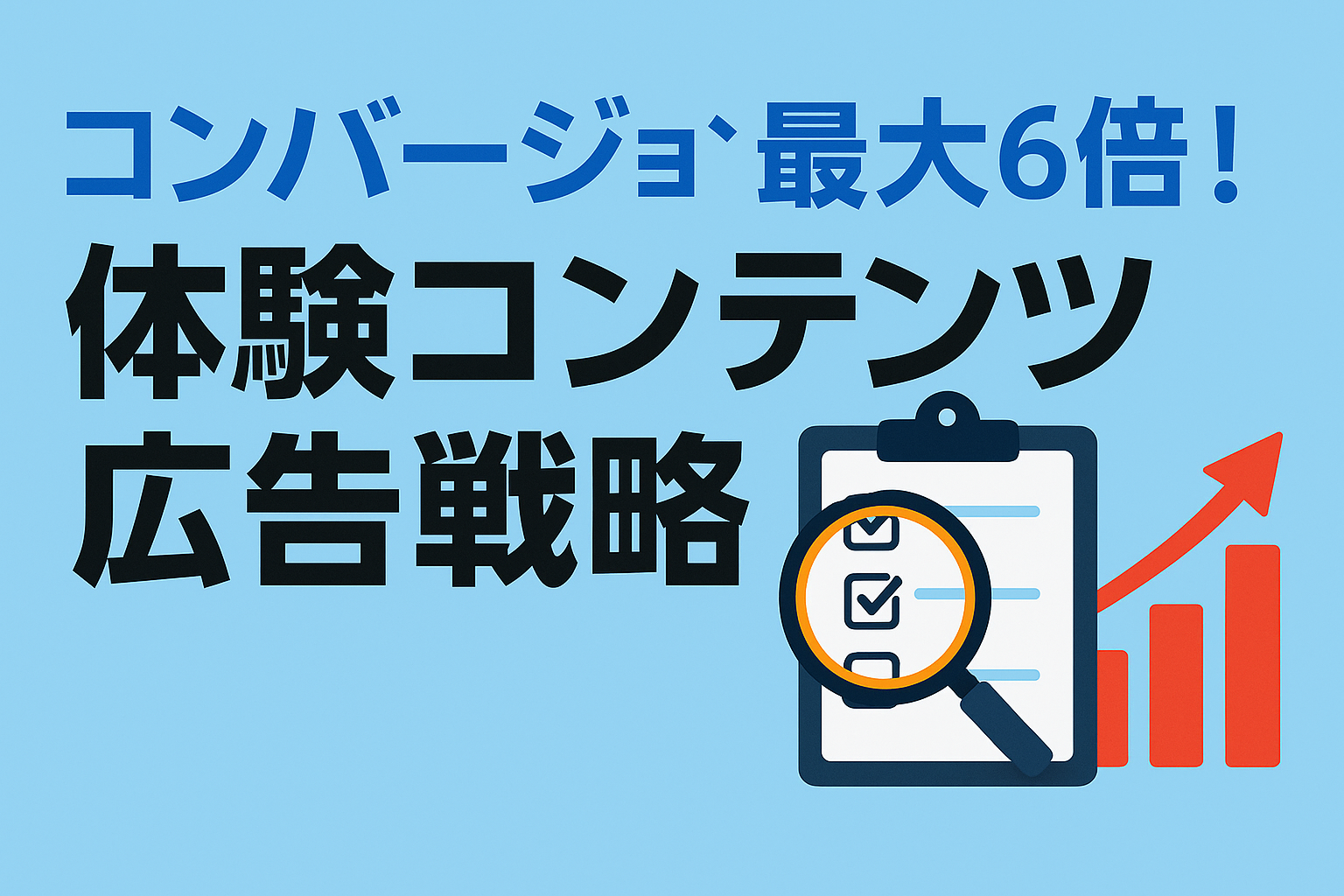
SNS広告の成果が頭打ちになっていませんか?
「CTRが伸びない」「CPAが下がらない」「広告が売り込みっぽいと感じられてスルーされる」
多くの広告運用者が、いま同じ壁にぶつかっています。
近年のSNSでは、ユーザーが企業広告よりも「リアルな体験」に反応する傾向が強まっています。
バナーや動画での訴求は“広告疲れ”を招きやすく、アルゴリズムの評価も伸びにくい。
そんな背景の中で注目されているのが、体験コンテンツ広告です。
体験コンテンツ広告とは、インフルエンサーや一般ユーザーが投稿した実体験コンテンツをそのまま広告として配信するSNS広告手法。
Meta社(Instagram・Facebook運営)も推奨する最新フォーマットで、ユーザーの共感×アルゴリズム適合の両立を実現します。
クリック率(CTR)は平均1.3〜1.5倍、コンバージョン率(CVR)は最大6倍まで伸びた事例もあり、
「広告を見てもらえない時代」に最適なアプローチとして導入企業が急増中です。
この記事では、SNS広告やデジタルマーケティングの現場で成果を上げたい担当者に向けて、
体験コンテンツ広告の基本・効果・運用方法・成功のポイントをわかりやすく解説します。
目次
執筆者:萩原 雄太
SNS・コミュニティマーケティング専門企業「LIDDELL」取締役。
みずほ証券でトップセールスを経験後、2017年よりLIDDELLに参画。上場企業含む多様なクライアントに対し、SNS戦略立案やファンマーケティングを推進。
AI・システム開発・コミュニティ設計にも関わり、100名規模のクラウドワーカーチームを統括している。
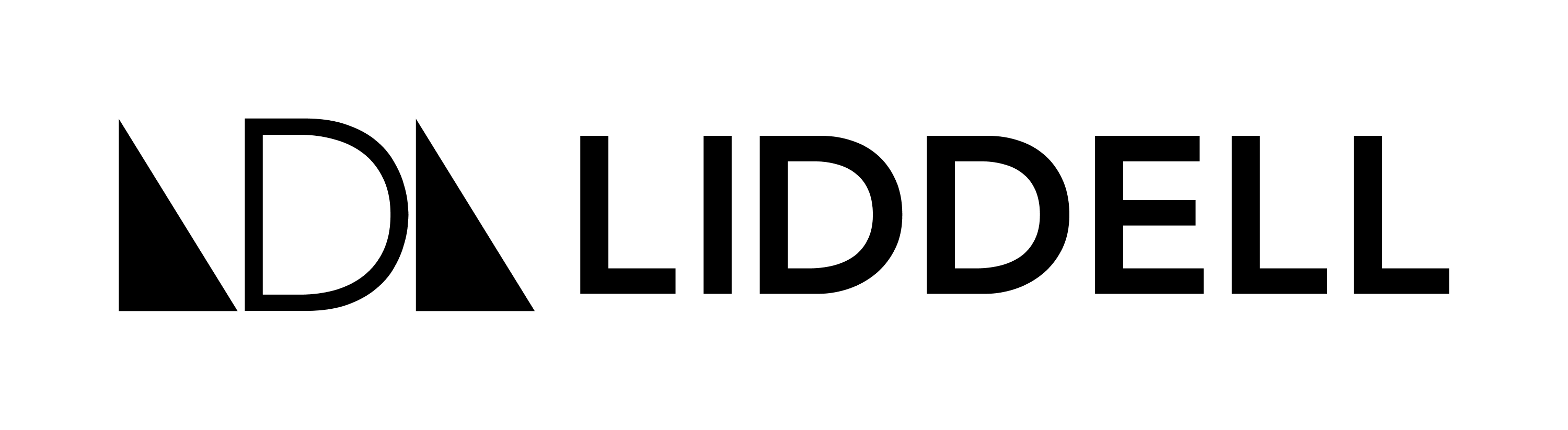
運営会社:リデル株式会社
SNS・インフルエンサーマーケティングに特化した企業。
7,000社以上との取引実績を持ち、50,000名を超えるインフルエンサーと連携。
マーケティング戦略からキャスティング、投稿運用、AI分析、Web3領域まで一気通貫で対応。
個人の影響力を活かした「共創型マーケティング」の実現を得意とする。
体験コンテンツ広告とは?Meta社推奨の配信手法
「広告は見られない」「リーチしても反応が薄い」そんな現場の悩みを背景に登場したのが体験コンテンツ広告です。
この手法は、インフルエンサーや一般ユーザーが投稿した“リアルな体験”をそのまま広告として配信するというもの。単なるレビューではなく、SNS上での自然な投稿に近い形で表示されるため、ユーザーに“押しつけ感”を与えません。
従来の企業アカウント発信型広告と違い、体験コンテンツ広告は「誰かの信頼できる発信」として受け取られます。
さらにMeta社(Instagram・Facebook運営)はこの手法を公式に推奨しており、アルゴリズム上も体験型・UGC型広告を優先的に配信する傾向があります。
つまり体験コンテンツ広告は、SNSユーザーが求める“リアルな共感”を生み出し、プラットフォーム側の最適化ロジックにも適合する、今もっとも成果を出しやすい広告フォーマットなのです。
体験コンテンツ広告の始め方:運用の流れと成功プロセス
体験コンテンツ広告は、ただ“投稿を広告に変える”だけでは成果を出せません。成功の鍵は、テスト設計とデータ活用にあります。以下は実際の運用プロセスです。
① インフルエンサーの選定とタイアップ投稿
まずは商品やブランドと親和性の高いインフルエンサーを選定します。フォロワー数よりも重要なのは「共感性」「発信トーン」「コメント欄での信頼度」。
ここで複数名にタイアップ投稿を依頼し、ABテストの素材を作ります。
② データ分析・クリエイティブの選定
各投稿の反応(いいね率・コメント率・保存数)を比較し、最もエンゲージメントの高い投稿を広告クリエイティブに採用。感情の動きやコメントの内容も分析対象にします。
③ 広告配信・最適化(PDCA)
選定した投稿を広告配信に活用し、CTR・CPC・CVRのデータをモニタリング。月次で改善を繰り返し、勝ちパターンを量産します。
初期は少額テストから始め、ROAS(広告費用対効果)400%以上を目標に拡張していくのが理想です。
④ 継続運用で資産化
体験コンテンツ広告の真価は継続データの蓄積。時期・商材・季節要因ごとの成果データを蓄積することで、クリエイティブ設計の精度が年々上がります。
体験コンテンツ広告が持つ3つの特徴
【特徴①】インフルエンサーの体験という「信頼」を広告として配信
ユーザーがSNSで最も信頼する情報源は、“企業”ではなく“他のユーザーの体験談”です。
体験コンテンツ広告では、その第三者のリアルな声を広告として届けるため、企業発信よりも圧倒的に受け入れられやすくなります。
「信頼できる人が使っているから気になる」という共感ベースの購買動機を自然に生み出せるのが、この手法の強みです。
【特徴②】SNSに馴染んだ、信頼度の高い広告配信が可能
一般的なSNS広告は“広告である”と分かった瞬間にスワイプされがちですが、体験コンテンツ広告は投稿主のアカウント名義で配信され、コメントややり取りもそのまま反映されます。
そのため、ユーザーのタイムラインに自然に溶け込み、「広告」ではなく「有益な体験情報」として受け止められます。
結果として、CTR(クリック率)・CPC(クリック単価)の改善が起きやすく、広告効率を高めながらブランド好感度も維持できるのです。
【特徴③】アルゴリズムにより広告配信効率が向上する傾向がある
各SNSプラットフォームでは、ユーザー体験を損なわない投稿を優先的に表示する設計が進んでいます。
体験コンテンツ広告はまさにその要件を満たしており、アルゴリズム上も“評価されやすい広告”として扱われるケースが増えています。
特にMeta社やTikTokでは「広告らしさを抑えた体験型コンテンツ」が推奨され、結果としてリーチ数・表示回数・クリック数の改善が期待できます。
体験コンテンツ広告を活用する3つのメリット
【メリット①】従来の広告よりも圧倒的なハイパフォーマンスで数値改善を実現
体験コンテンツ広告は、CTR(クリック率)で120〜140%、CPC(クリック単価)で20〜40%改善する傾向があります。
実際、ある化粧品ブランドのInstagram広告では、CV(購入数)が6倍に伸びた事例も。
理由は明快で、ユーザーが「信頼できる第三者の声」をもとに行動しているからです。
広告効率を高めたいマーケターにとって、最も費用対効果の高い打ち手の一つといえます。
【メリット②】ユーザーの購入意欲を通常の4倍に向上
Meta社のデータによると、インフルエンサーの体験をきっかけに知った商品は、通常の広告に比べて購入意欲が4倍に上がると報告されています。
単なる「商品紹介」ではなく、“リアルな使用感”が伴うストーリーがあることで、ユーザーの心理的なハードルが下がり、購入率が向上します。
【メリット③】UGC(ユーザー生成コンテンツ)の発生を促進できる
誰かの体験を見て商品を購入したユーザーは、自分の体験も共有したくなる傾向があります。
つまり、体験コンテンツ広告を起点にUGCが自然発生しやすくなるのです。
マス広告由来の投稿率が5%前後なのに対し、インフルエンサー発信経由では約95%がSNSで体験を共有するというデータも。
このUGC循環が生まれることで、広告の効果はキャンペーン終了後も持続します。
まとめ:体験コンテンツ広告で「共感される広告」へ
従来の広告が“押す”ものだとすれば、体験コンテンツ広告は“寄り添う”広告です。
ユーザーが自ら見たい・知りたいと思える体験情報を中心に置くことで、信頼・自然拡散・効率化のすべてを同時に実現できます。
「広告を見てもらえない」「CPAが上がり続けている」と感じる方こそ、体験コンテンツ広告へのシフトを検討する価値があります。




